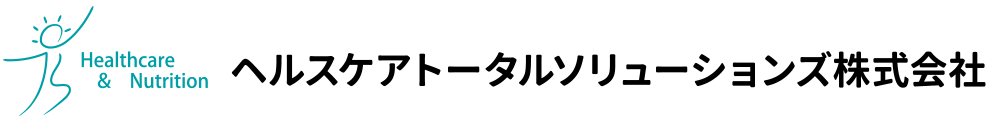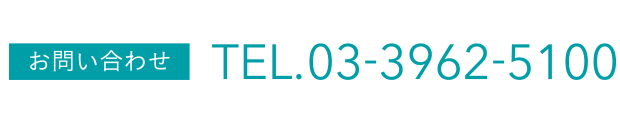マグロ

毎年、年明けの風物詩として話題になるのが、マグロの初競りです。
なかでも「一番マグロ」は、その年最初の競りで最も高値を呼ぶ存在として注目を集めます。前年に水揚げされたマグロの中で、大きさだけでなく、脂や色も基準に選ばれ、実際の価格以上のご祝儀相場的価格には、「景気づけ」という意味合いが込められています。
マグロの旬
旬は一般的に冬の12~1月頃とされていますが、回遊魚のため年によって時期が前後することがあります。また、産地によっても旬の時期は異なります。例えば、青森県大間で水揚げされるクロマグロは9~12月が旬とされる一方、同じ青森県でも深浦町で獲れるものは、脂が乗る6~7月が旬の時期となります。
マグロの歴史
マグロの歴史は意外に古く、縄文時代までさかのぼるといわれています。
縄文時代の貝塚からマグロの骨が出土していることが、その裏付けとなっています。
また、マグロは鮮度が落ちやすい魚であるため、現代のように交通網や冷蔵技術が発達していなかった江戸時代には、価値の低い魚とされていました。この時代は人力での輸送が主流だったため、沿岸の漁場から江戸の町まで運ぶだけで時間がかかり、マグロの鮮度を保つことは困難でした。その結果、刺身で食べると食あたりを起こすこともあり、マグロは「下魚(げざかな)」と呼ばれていたとされています。
そこで生まれたのが「漬け(ヅケ)」という調理法です。鮮度が落ち始めたマグロを醤油に漬け込むことで、品質の低下を抑える工夫がなされました。
現代でも親しまれている「マグロの漬け」は、こうした知恵から生まれた料理であり、マグロ料理の中でも最も古いレシピのひとつかもしれません。
「ねぎま」の「ま」は、実はマグロの「マ」
焼き鳥で知れ渡っている「ねぎま」は、ひらがなやカタカナで表記されることがほとんどですが、漢字ではどう書くかを考えたときに、「葱間」、つまり「ネギの間に鶏肉を刺すから“葱間”」と考える方も多いのではと思います。しかし、正しくはねぎまの「ま」は「間」ではなく、“マグロ”の「ま」を指しています。
その起源は、江戸時代に人々の間で親しまれていた「葱鮪鍋(ねぎまなべ)」という鍋料理です。江戸時代末期、マグロは赤身を醤油漬けにして食べられていましたが、脂の多いトロは保存しにくく、捨てられることもありました。この余りがちだったトロをネギと煮込んだ料理が葱鮪鍋です。その後、ネギとマグロを串に刺して焼く「ねぎマグロ」が生まれ、現在の「ねぎま」の原型になったとされています。
マグロの種類
マグロはスズキ目サバ科マグロ属でサバの親戚です。
マグロは8種類存在すると言われています。

・クロマグロ
「マグロの王様」として知られ、ホンマグロとも呼ばれています。成長段階によって呼び名が変わり、小型のものはヨコワやメジ、ヒッサゲなどと呼ばれます。
良質な脂が乗り、色合い・香り・旨味のバランスに優れていることから「黒い海のダイヤ」とも称されています。赤身から大トロまで部位ごとの味の違いがはっきりしており、刺身や寿司でその魅力を最大限に楽しめる高級魚です。
・ミナミマグロ
主にインド洋で漁獲されることからインドマグロとも呼ばれています。メバチマグロよりも脂肪分が多く、卸した身は赤黒く、コクのある味わいが特徴です。クロマグロに近い風味を持つことから、高級寿司店や料理店で好まれる傾向があります。
・メバチマグロ
その名の通り目が大きいことから名付けられたといわれています。日本国内で流通しているマグロの中でも最も取扱量が多く、スーパーや飲食店で「マグロ」として販売されているものの多くがこのメバチです。赤身が中心でクセが少なく、価格と品質のバランスが良いため、刺身や漬け、丼ものなど幅広い料理に使われています。
・キハダマグロ
マグロの中で最も漁獲量が多く、ツナ缶などの加工食品の原料として広く利用されています。脂肪分が少なく、トロと呼ばれる部分がほとんどないため、他のマグロに比べてあっさりとした味わいが特徴です。その分、1キロ当たりの単価も比較的安価で、漬けやフライ、ステーキなど加熱調理に向いています。
・ビンナガマグロ
別名ビンチョウとも呼ばれ、身の色が淡いピンク色をしているため、他のマグロと区別しやすいのが特徴です。近年では回転寿司で定番となっており、「ビントロ」とはこのビンナガの脂の乗った部分を指します。価格の割に脂があり、コストパフォーマンスが高いことから重宝されています。
マグロの部位

カマ:マグロのエラの近くの部分がカマになります。名前の由来は、色や形がそっくりな「鎌」から名づけられました。カマのすぐ横には大トロがあり、脂が乗っていて安いのに実は一番美味しいとも言われています。
大トロ:腹身の最も脂が多い部分です。 特にカマ下のカマトロは非常に美味しい部分です。
マグロの部位の中で最も値段が高く、寿司店でも高級な寿司ダネとして扱われています。
中トロ:腹身と背身にあり、大トロ、赤身、血合いをのぞいた部分。 適度に脂が乗っているのが特徴です。 程よくとろける脂の乗りと赤身の旨みのバランスがうまく調和し、寿司や刺身はもちろん、炙りでも美味しく頂けます。
赤身:背側にあり、脂が少なく身は硬め、低エネルギー、高たんぱくな部分です。 寿司店では、赤身は「マグロ」の名称で呼ばれることが多く、その値段は大トロや中トロと比べて安いですが、特有のどっしりとした重量感ともちっとした食感から常に人気です。
栄養的特徴
マグロはEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)をはじめ、たんぱく質や鉄分、ビタミンDなどのさまざまな栄養素を含んでいます。とくに注目すべきはDHAの含有量で、魚の中でもトップクラスです。
EPA・DHA
EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、まぐろの脂質に多く含まれています。これらは動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの病気を防ぐ働きや、多様な健康効果がある成分として注目されています。
これらは体内で作ることができないため、魚などの食品から摂取する必要があります。また、中性脂肪の合成を抑える働きがあり、血中中性脂肪の低下につながることから、特定保健用食品(トクホ)にも利用されています。
マグロは刺身やたたきなど、油を使わずに調理できるため、脂質やエネルギーを抑えながらEPA・DHAを摂取しやすいのも特徴です。また、加熱による成分の損失が少ない生食では、EPA・DHAを効率よくとることができます。
たんぱく質
たんぱく質は、筋肉や細胞の材料となり、私たちの体が作られる際に欠かせません。極端に不足することで、免疫機能の低下が起こることも知られています。筋肉をつけたいトレーニング中の方やダイエット中の方、食事量が低下してきた高齢者など、さまざまな年代で不足することなく補いたい栄養素です。
マグロはたんぱく質を多く含む上に、脂質が少ないため、エネルギーを抑えながらたんぱく質を補給できます。

鉄分
鉄分は、血液中の赤血球を作る材料となり、酸素を全身に運ぶ働きを助ける栄養素です。鉄分が不足することで起きる貧血は、疲れやすさやめまい、息切れ、頭痛など、さまざまな不調を引き起こす原因となります。
マグロに含まれる鉄分は「ヘム鉄」といい、吸収率が65%ほどと高いことが知られています。ヘム鉄はタンパク質に包まれていて吸収しやすいかたちになっているため、他の食品と一緒に摂っても、吸収を妨げられることはなく、比較的簡単に鉄分を摂取できます。種類や部位によって異なりますが、特に赤身部分に鉄分が多く含まれています。

ビタミンD
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける働きがあり、骨の健康づくりに必要です。
ビタミンDが不足すると、骨粗しょう症や骨折のリスクが高まることが知られています。
マグロは、魚の中でも脂質にビタミンDが多く含まれる特性があり、特に脂の乗ったトロ部分に豊富です。100gあたり9.0~18.0㎍程度のビタミンDを含み、成人の1日摂取目安量(8.5㎍)を十分に補うことができます。
マグロの良い点
手軽に食べられる
刺身や寿司、たたきなど、マグロは購入後そのまま食べられるものが多いので、調理の手間がかからず忙しいときでも取り入れやすい食材です。刺身用のサクや切り身で販売されていることも多く、生食だけでなく、焼き魚などにしても骨を気にせず食べやすいのが特徴です。
調理の幅が広い
マグロは刺身以外にも、焼き物、和え物、揚げ物、漬けなど、さまざまな料理に活用できます。唐揚げやカツにすると肉のような食感になり、食べ応えが増すため、主菜としての満足感も得られます。
マグロの注意点
食べ過ぎに注意
マグロなどの大型魚は、食物連鎖の影響によりメチル水銀が体内に蓄積しやすい特徴があります。毎日のように食べたり、1回の量が多い状態が続くと、体への影響が心配されることがあります。
刺身や丼など1食あたりのマグロの量が多い日が続かないようにし、他の魚(さけ・あじ・さば等)や肉類と入れ替えることを意識しましょう。1回の量を適量にし、頻度を調整することで、栄養の良さを活かしながら安心して取り入れることができます。
取り入れ方、活用方法
摂取量の目安:
1日の適量は約50g(刺身5切れ程度)が目安になります。
選び方:
鮮度はトロも赤身も赤い色に深みがあり、鮮やかなものを選びましょう。鮮度が落ちると酸化して褐色がかってくるのでわかります。
サクを選ぶポイント:
マグロをサクで購入する際は、表面の筋目を確認すると品質の目安になります。筋がサクに対してタテに、同じ間隔で入っているものは、身質が整っていて良質、逆に筋目の間隔が極端に狭いものや、白い筋がはっきり見えるものは、味や食感が劣りやすいと言われています。
また、サクの切り方として、斜めに筋が入っているも の、さらに木の年輪のように筋が入っているものは、食感がかたく感じやすくなります。
の、さらに木の年輪のように筋が入っているものは、食感がかたく感じやすくなります。
余ったマグロの保存方法
冷凍保存【保存目安:冷凍で約1~2週間】
マグロのサクは水分をキッチンペーパーでしっかりふき取り、
ラップで包み、さらに空気が入らないよう密閉袋に入れて冷凍庫で保存します。
解凍する際はキッチンペーパーまたは布巾で包み、その上からラップを巻いて冷蔵庫で
3~5時間を目安にゆっくり解凍しましょう。
漬け保存【保存目安:冷蔵庫で半日~1日程度】
マグロの赤身を、しょうゆ:みりん=1:1の漬けだれに浸すことで、風味を保ちつつ保存性が高まります。大葉や白ごまなどを一緒に漬けると、風味づけになり減塩にもつながるのでおすすめです。
※みりんは軽く煮切ることでアルコール臭を抑え、味がなじみやすくなります
※長時間漬けると塩分が強くなるため、漬け時間は短めにしましょう
他の食材とのおすすめの組み合わせ
ビタミンCを含む食品と合わせる
マグロに含まれる鉄分は、ビタミンCと一緒にとることで吸収率が高まります。しかし、マグロ自体にはビタミンCはほとんど含まれていません。
そのため、ブロッコリーやパプリカ、ピーマン、トマトなどの野菜や、レモンをかけるなどの工夫で補うのがおすすめです。副菜や付け合わせとして取り入れると、栄養バラ ンスが整いやすくなります。
ンスが整いやすくなります。
カリウムを含む食品と合わせる
刺身や丼などでマグロを食べる際は、しょうゆなどで塩分が多くなりがちです。カリウムは体内の余分な塩分の排出を助ける働きがあります。
そのため、アボカド、ほうれん草、きゅうり、長芋などのカリウムを多く含む食材を食事の際に一緒に取り入れることで、より健康的な組み合わせになります。
カルシウムを含む食品と合わせる
マグロに含まれるビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける働きがありますが、マグロ自体にはカルシウムがほとんど含まれていません。
そのため、チーズや牛乳などの乳製品、ほうれん草・小松菜・水菜などの色の濃い野菜を、汁物の具材や副菜として組み合わせるのがおすすめです。
おすすめレシピ
適度な脂質を含み、食物繊維やビタミンE、カリウムを含むアボカドを組み合わせることで、栄養バランスもよくなり、腹持ちがよい満足感が高まる一品に。シンプルな調理ですが、栄養価が高く、忙しい日にも手軽に作れるレシピです。
マグロとアボカドのポキ丼
〈材料(1人分)〉
・マグロ(刺身用) 50g
・アボカド 1/2個
・玉ねぎ 1/8個
・ミニトマト 2個
・白ごま 少々
・しょうゆ 小さじ3
・ごま油 小さじ1/2
・みりん 小さじ1
・ごはん 茶碗1杯分(約120g)
【作り方】
1.マグロとアボカドは1.5cm角に切り、玉ねぎはスライスして水にさらし、水気を切ります。
2.ボウルに調味料を入れて混ぜ、マグロを10分ほど漬ける。
※みりんのアルコールが気になる場合は、電子レンジで軽く加熱して煮切ってから使いましょう
3.2に玉ねぎ、アボカドを加えて軽く混ぜ合わせます。
4.丼にごはんを盛り、3をのせ、白ごまを散らして完成です。
【アレンジ】
・刻みのりや温泉卵をトッピングしてもおすすめです。
・玉ねぎの代わりにきゅうりを使うと、さっぱり食べやすくなります。